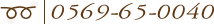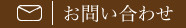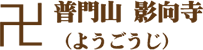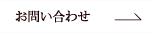日本の四季を表す暦 七十二侯 十一月二十一日〜十一月二十五日 五十八侯 小雪 初侯 虹蔵不見(にじかくれてみえず) 虹を見かけなくなる 旬の言葉 『時雨しぐれ』 時雨は、冬のはじめに降るにわか雨のことです。 一時的な通り …
Blog Archives
Blog Archives
金盞香
日本の四気を表す暦 七十二侯 十一月十七日〜十一月二十日 五十七侯 立冬 末侯 金盞香(きんせんかさく) 水仙の花が咲く 旬の花木『水仙』 ヒガンバナ科スイセン属の花である水仙。水仙は、学名を「ナルキッソン」と言います。 …
地始凍
日本の四気を表す暦 七十二侯 十一月十二日〜十一月十六日 五十六侯 立冬 次侯 地始凍(ちはじめてこおる) 大地が凍り始める 旬の行事【七五三】 子どもの成長を祝い、子ども自身にもその自覚を与えるための儀式が七五三で、男 …
山茶始開
日本の四気を表す暦 七十二侯 十一月七日〜十一月十二日 五十一侯 立冬 初侯 山茶始開(つばきはじめてひらく) 山茶花が咲き始める この(山茶)つばきは、椿(つばき)を指しているのではなく、ツバキ科の山茶花の事をさしてい …
本日より、立冬です。
本日より、二十四節季 【立冬】になります。 木枯らしが吹き始め、冬の気配を間近に感じる頃。 暦の上では、すでに冬になりました。 只今、二十四節季御朱印は 霜降 立冬 小雪をお渡し致しております。
楓蔦黄
日本の四気を表す暦 七十二侯 十一月二日〜十一月六日 五十侯 霜降 末侯 楓蔦黄(もみじつたきばむ) もみじや蔦が黄葉する 今日は何の日 十一月三日 文化の日 1946年のこの日、日本国憲法が交付されたことを記念し「自由 …
霎時施
日本の四気を表す暦 七十二侯 十月二十八日〜十一月一日 五十侯 霜降 次侯 霎時施(こさめときどきふる) 小雨がしとしと降る 今日は何の日 十月三十一日 ハロウィン 「ハロウィン」は、もともとは古代アイルランドのケルト族 …
霜始降
日本の四気を表す暦 七十二侯 十月二十三日〜十月二十七日 五十侯 霜降 初侯 霜始降(しもはじめてふる) 霜が降り始める 旬の食材 牛蒡(ごぼう) 平安時代から薬草として中国から日本へ伝来したと言われていますが、食用とさ …
本日より、霜降です。
本日より、二十四節季 【霜降】になります。 さざんかの花が開き、朝晩の草木が霜をまとうようになると初霜がおります。日が落ちるのがだんだんと早くなり、秋の夜長が訪れます。 只今、二十四節季御朱印は 寒露 霜降 立冬をお渡し …
蟋蟀在戸
日本の四気を表す暦 七十二侯 十月十八日〜十月二十二日 五十侯 寒露 末侯 蟋蟀在戸(きりぎりすとにあり) 蟋蟀が戸の辺りで鳴く 蟋蟀は、正しくは「しっしゅつ」といい、コウロギやきりぎりすのことを指します。 秋の虫の中で …