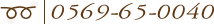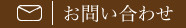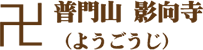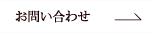本日より、二十四節季 【小寒】になります。 この小寒から、およそ一ヶ月を『寒』と呼び、特別に寒い時期だとされています。そんな『寒の入り』の夜の翌朝に、健康を願って粥を食べる習慣が平安時代より受け継がれています。 只今、二 …
Blog Archives
Blog Archives
雪下出麦
日本の四気を表す暦 七十二侯 十ニ月三十一日〜一月四日 六十六侯 冬至 末侯 雪下出麦 (ゆきわたりてむぎいだす) 雪の下で麦が芽を出す 旬の行事『除夜の鐘』 除夜の鐘は、大晦日から元旦にかけての深夜に寺院の梵鐘を百八回 …
鹿角解
日本の四気を表す暦 七十二侯 十ニ月二十六日〜十二月三十日 六十五侯 冬至 次侯 鹿角解 (さわしかのつのおつる) 大鹿の角を落とす 旬の生き物『大鹿』 鹿は秋の季語として、「古今和歌集」や「新古今和歌集」などの和歌に詠 …
本日より 冬至 です。
本日より、二十四節季 【冬至】になります。 日が一番短い冬至。日が一番短いとは、この日を境にだんだん日が長くなるということ。 太陽が生まれ変わる日とされ、この日を『一陽来復』と称し、陰が弱まり陽の気が復活してくれると考え …
乃東生
日本の四気を表す暦 七十二侯 十ニ月二十一日〜十二月二十五日 六十四侯 冬至 初侯 乃東生 (なつかれくさしょうず) 夏枯草が芽を出す 旬の花木『千両万両』 正月が近くなると縁起物として販売される、冬に真っ赤に熟す果実が …
鮭魚群
日本の四気を表す暦 七十二侯 十ニ月十七日〜十二月二十一日 六十二侯 大雪 末侯 鮭魚群 (さけのうおむらがる) 鮭が群がり川を上がる 旬の魚『鮭』 冬の魚の代表格の鮭。 川で生まれた鮭が海に出てかいゆうし、また生まれた …
大雪
本日より、二十四節季 【大雪】になります。 雪の結晶は、美しい六角形をしている事から、六花とも呼ばれます。これらが風花となって舞うこともあれば、粉雪となってさらさらと降り注ぐこともあり、様々な表情を見せながら、景色を一面 …
閉塞成冬
日本の四気を表す暦 七十二侯 十ニ月七日〜十二月十一日 六一侯 大雪 初侯 閉塞成冬 (そらさむくふゆとなる) 天地の気が塞がって冬となる 旬の鳥『白鳥』 白鳥はカモ科の大型水鳥で、日本に渡来越冬する渡り鳥です。日本に渡 …
朔風払葉
日本の四気を表す暦 七十二侯 十一月二十七日〜十二月一日 五十九侯 小雪 次侯 朔風払葉 (きたかぜこのはをはらう) 北風が木の葉を払い除ける 旬の食材『はくさい』 鍋料理の具材として欠かすことのできない冬の野菜といえば …
本日より、小雪です。
本日より、二十四節季 【小雪】になります。 北風が吹き、山の頂には雪が積もる頃。鎮守のようにどっしりと構える太い銀杏が黄色に染まる姿は頼もしいものです。また、小春日和とは、十一月から十二月にときおり訪れる暖かな春のような …