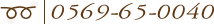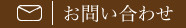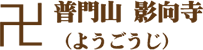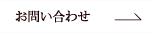日本の四気を表す暦 七十二侯 ニ月八日〜ニ月十二日 ニ侯 立春 次侯 (うぐいすなく) 鶯が山里で鳴き始める 旬の鳥『鶯』 「春告鳥」とも呼ばれ、ホーホーケキョという独特の鳴き声が古くから愛されてきた鳥。 夏は山地の低木 …
Blog Archives
Blog Archives
東風解凍
日本の四気を表す暦 七十二侯 ニ月三日〜ニ月七日 一侯 立春 初侯 東風解凍 (こちこおりをとく) 東風が厚い氷を溶かし始める 旬のことば『春一番』 立春の頃、その年初めて吹く強い南風が春一番です。発達した低気圧が日本海 …
本日より、立春です。
本日より、二十四節季 【立春】になります。 旧暦では、立春が新年の始まりでした。この日から立夏までが、暦の上で春となり、立春の前日が節分となります。 春の節分は、最も重要視されており季節の変わり目は魔が生じやすいと言われ …
鶏始乳
日本の四気を表す暦 七十二侯 一月二十九日〜二月二日 七十二侯 大寒 末侯 鶏始乳 (にわとりはじめてとやにつく) 鶏が卵を産み始める 今日は何の日『節分』 節分は、二月三日のみならず、本来であれば立春、立夏、立秋、立冬 …
水沢腹堅
日本の四気を表す暦 七十二侯 一月二十五日〜一月二十九日 七十一侯 大寒 次侯 水沢腹堅 (さわみずこおりつめる) 沢に氷が厚く張りつめる 旬の花木『福寿草』 キンポウゲ科フクジュソウ属の多年草で、別名を「元日草」、ある …
款冬花
日本の四気を表す暦 七十二侯 一月二十日〜一月二十四日 七十侯 大寒 初侯 款冬華 (ふきのはなさく) 蕗の薹が蕾を出す 旬の花木『蕗の薹』 キク科フキ属の多年草てあるフキから、早春になって花茎が伸びてきた …
本日より 大寒です。
本日より、二十四節季 【大寒】になります。 大寒の名のごとく、一年のうちでもっとも寒い時期です。空気が澄み渡る早朝などは、寒気が肌にささるようです。この時期に二十日正月を迎えます。元旦から二十日目の日のことで、正月の終わ …
雉始雊
日本の四気を表す暦 七十二侯 一月十五日〜一月十八日 六十九侯 小寒 末侯 雉始雊 (きじはじめてなく) 雄の雉が鳴き始める 旬の鳥『雄のキジ』 日本の国鳥であるキジは日本では北海道と、対馬を除く本州四国九州に棲息してお …
日本の四気を表す暦 七十二侯 一月十日〜一月十四日 六十八侯 小寒 次侯 水泉動 (しみずあたたかをふくむ) 地中で凍った泉が動き始める 旬の行事『鏡開き』 鏡開きとは、一月十一日に今年一年の家族円満を願いながら神様にお …
芹乃栄
日本の四気を表す暦 七十二侯 一月五日〜一月九日 六十七侯 小寒 初侯 芹乃栄 (せりすなわちさかう) 芹がよく生育する 旬の花木『セリ』 春の七草としてもおなじみのセリ。最近では時季になるとスーパーなどでも売られている …